気候変動に適応した農業技術に関する研修会や気候変動に関するセミナー等の紹介です。
研修会等のタイトルをクリックすると、開催要領等詳細を見ることができます。
1 気候変動に適応した農業技術に関する研修会等
現在、農業・園芸総合研究所(農園研)、古川農業試験場(古試)、畜産試験場(畜試)で取り組んでいる気候変動に適応した農業技術の実施中の試験研究やこれまでの試験研究の成果に関する研修会等を掲載しています。
宮城県が開催する研修会等
※現在、ご案内できる研修会等はありません。
国や関係機関等が開催する研修会等
2 気候変動に関するセミナー等
宮城県が主催する気候変動に関するセミナー等のほか、関係機関が主催するセミナー等も掲載しています。
宮城県が開催するセミナー等
※現在、ご案内できるセミナー等はありません。
国や関係機関等が開催するセミナー等
既に終了した研修会、セミナー等
既に終了した研修会、セミナー等の情報、過年度の情報については、以下のページで確認できます。
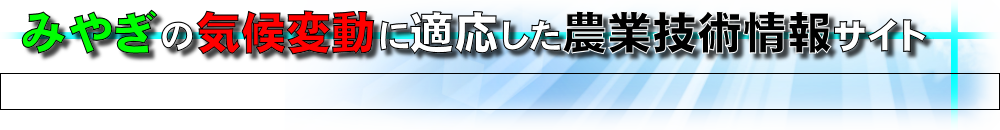
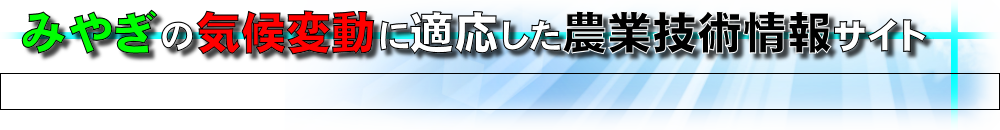
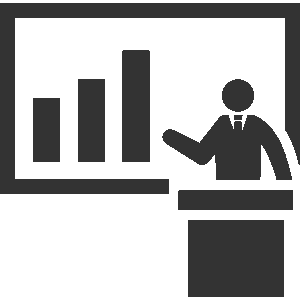 研修会等開催案内
研修会等開催案内